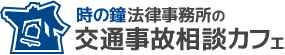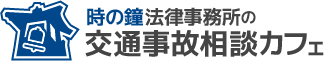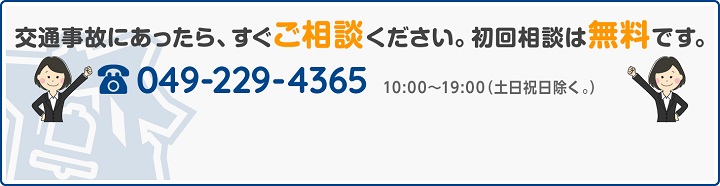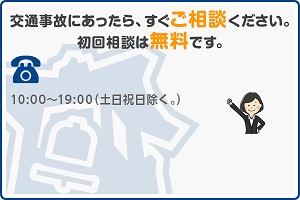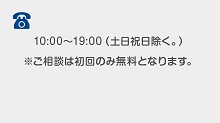交通事故の対応方法などよくある質問
-


当事務所によせられる質問集
交通事故には様々なパターンがございますが、少しでも皆様の不安のご解消に役立てればと、当事務所によくある質問を具体的な事例を交え、ご紹介いたします。
A.交通事故により、ケガが完全回復せずに一定の回復しない障害を負ってしまった場合、後遺障害が認定されます。障害の重度は一番重い1級~14級までの設定になっており、障害認定は「損保保険料自賠責損害調査センターの調査事務所」によって決定します。
A.ケガの状態によっても変わってきますが、一般的には3ヵ月~6か月程度が治療期間として認められる場合が多いようです。また、あくまで治療費として認められるのは、その事故によって発生したケガのみです。
A.通院先を決めるのは、ご本人様です。保険会社によっては病院を指定する保険会社さんもいますが、通う病院や接骨院を決めるのは、被害者であるご本人です。
A.国は、自動車損害賠償保障法に基づく保障事業を行っていますので、傷害事故の上限は120万円、死亡事故の上限は3000万円、後遺障害事故の上限は4000万円(物損のみの場合は、保障の対象になりません。)を求めることが可能です。請求権の時効は2年で、請求できる主な内容は請求の具体的窓口・手続は、自己の保険会社に確認するのが好ましいです。
A.交通事故の被害者が受ける損害には様々な種類がありますが、主に次のようなものがあります。
【死亡事故】の場合
- 逸失利益(死亡してしまった人が、交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)
- 死亡するまでに入院をしていた場合には、その入院中にかかった費用
- 葬儀費用
- 慰謝料
【傷害事故】の場合
- 怪我の治療費
- 付添看護費用
- 入院・通院のための交通費や雑費
- 介助器具などの費用
- 仕事ができなかったことによる休業損害
- 入院・通院についての慰謝料
- 後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料
【物損事故】の場合
- 自動車その他損傷したものの修理費用や買い替え費用
- 自動車修理の間の代車費用
- 休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害)
上記以外にも場合によっては損害賠償の対象となるものもありますので、詳しくは当事務所にご相談ください。
A.大事に至らなければ良いのですが、後で異常が生じても加害者の身元も不明では何もできません。事故にあったときは、例え軽いと思っても、車のナンバーと加害者の住所氏名くらいは免許証を見せて貰ってメモしておきます。自動車には車検証、自動車責任賠償保険証を常備しているはずですから車の所有者、保険会社名、保険証のナンバー等をメモさせて貰ってください。
なお、加害者には被害者を救助保護する義務、事故の内容を警察に通報する義務があります。お互いの為に警察に通報しておくことです。被害者の損害賠償請求にとって事故当時の状況は大事な証拠になります。警察が来て実況見分調書を作っておいてもらうこと、目撃者に住所氏名を聞いておくこともできたらしておきたいところです。
民事上の責任と、刑事上、行政法上の責任は全く別個のものです。示談により民事上の責任は免れても、刑事上の責任においては、情状の面で被害者に対する誠意を示すものとして示談が斟酌される事はあっても、刑事責任そのものは示談したからといって免れるものではありません。
行政法上の責任は民事・刑事の責任と別個のものですから同様です。
A.父親が被害者として請求できるはずであった損害賠償請求権を相続人が相続によって取得し行使することになります。また、死亡した人の配偶者や子供等の近親者は、独自の慰謝料請求権もあります。従ってあなた方母子が損害賠償請求できます。叔母さんがあなたの父親によって扶養されていた等特別な事情のある時は、近親者としてその叔母さんにも独自の請求権が認められる場合もあります。
交通事故の示談は、加害者が被害者に一定の損害賠償金を支払って、被害者は加害者に対し、この金額以上の損害賠償請求をしないと言う約束をすることをいいます。双方の言い分が食い違っている場合にはお互いに譲歩しあってこの約束をするわけです。
この約束は民法上和解契約といわれるもので、示談が詐欺強迫や錯誤によってなされたり内容が公序良俗違反である等特別な事情の無い限り将来も守らなければなりません。但し、例外的に、示談後に示談当時には予想できなかった後遺症が生じたような時は、示談の前提事項に事情の変更があったものと考える等して、後遺症の程度に応じた損害賠償をあらためて請求できる場合があります
A.人身事故を起こし相手に怪我を与えた場合、その事故の経緯と相手方の怪我の度合いによっては刑事処分が課せられます。刑事処分の種類としては,刑事処分の種類については,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第86号)に規定されております。この法律は,これまで刑法に規定されていた自動車の運転によって人を死傷させる行為に対する刑罰の規定を独立させたものです。
尚、人身事故を起こしたからといって,必ずしも刑事処分が科せられるわけではありません。事故の内容によっては相手の怪我の程度が比較的軽く,更に被害者が加害者に対し罪を軽減させてほしいといった申し出があった場合には,刑事処分が課せられない可能性もあります。
刑事処分の流れとしては、刑事処分にあたるかどうかについての警察による捜査、そして、刑事処分の対象になるとすれば,どのような処分をするか,という検察官による判断となります。
検察官がする刑事処分の種類には、①不起訴処分,②起訴猶予処分,③略式処分,④起訴処分の4つがあります。
①不起訴処分とは、公訴を提起しないという処分です。 つまり、この場合,刑罰は課されないことになります。
②起訴猶予処分とは、犯罪は成立するのですが、公訴の必要がないとして不起訴にするという処分です。 つまり、不起訴処分と同様、刑罰は課されません。
③略式処分とは、公判を開かず、書面審理だけで刑を言い渡して手続きが終了する処分です。略式裁判を認めれば,後日簡易裁判所から判決文が送付された書面が特別送達により送付されます。
④起訴処分とは、公判が開かれる(裁判所で審理が行われる)処分です。 検察官が起訴処分を選択すると、公判が開かれ、裁判官が証拠に基づいて有罪か無罪か(犯罪事実の有無)を判断します。有罪の場合は、情状を考慮して刑を定め、判決を言い渡すことになります。
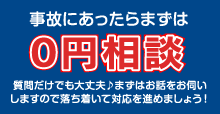

-

- 所在地情報
- 〒350-0045
埼玉県川越市南通町1-5 クリオ川越壱番館105号室
- TEL
- 049-229-4365
- FAX
- 049-229-4367
- アクセス
-
東武東上線川越駅から 徒歩4分
JR川越駅東口 徒歩4分
駐車場無し
 代表弁護士 渡邉 晋
代表弁護士 渡邉 晋
埼玉弁護士会
第24867号
事故にあった時は、不安なものです。
どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい!
©TOKINOKANE-Law Office.